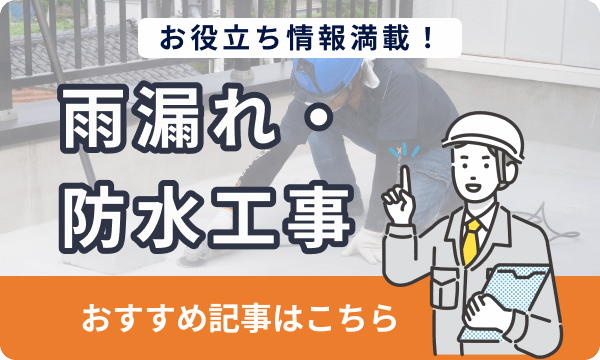<こんな疑問のある方におすすめ>
・ビル・マンションの屋上防水の耐用年数ってどれくらい?
・防水のメンテナンスはどれくらいの周期で行ったらいいの?
・防水工事の費用は経費として計上できる?
常に雨風にさらされる屋上や外壁の防水性能は、建物の寿命を左右するほど大切なものです。防水機能の耐用年数がわかれば、適切なメンテナンス時期を把握できます。
この記事では、工法別の防水工事の耐用年数やメンテナンス周期を解説するほか、防水工事費用を経費として計上する方法も紹介します。ぜひ参考にしてください。
防水工事の耐用年数は10~20年
工法によって多少違いはあるものの、一般的に防水工事の耐用年数は10~20年といわれています。メンテナンスは、施工後10年を目安に行いましょう。メンテナンスを怠ると、ひび割れなどの劣化部分から水が侵入し、雨漏りや建物内部の損傷の原因となります。
耐用年数と耐久年数は別物
防水工事の「耐用年数」と似た言葉に「耐久年数」があります。この2つは同じようで、意味が異なる点に注意が必要です。
「耐用年数」とは、財務省が定めた固定資産の価値があるとみなされる年数を指します。10万円以上の固定資産に対して定められ、防水工事の場合は工法や使用する資材によって異なります。物理的な寿命でなく、資産として価値があると定められた寿命です。
「耐久年数」とは、住宅メーカーや施工業者が独自の基準で定めた物理的な寿命を指します。建物として問題なく使える年数で、メーカーや業者ごとに異なります。
防水工事の種類別の耐用年数
防水工事の種類は、主に4つです。工事の種類別の耐用年数を表にまとめました。
| 防水工事の種類 | 耐用年数 |
| ウレタン防水 | 密着工法:7~10年通気緩衝工法:10~15年 |
| FRP防水 | 10~12年 |
| シート防水(塩ビ・ゴム) | ゴムシート:10~15年塩ビシート:10~20年 |
| アスファルト防水 | 15~25年 |
ウレタン防水は、どの工法で工事するかによって耐用年数が変わります。またシート防水は、シートの素材によって耐用年数が異なる点がポイントです。
屋上防水工事が必要なサイン
日頃から紫外線や雨風にさらされる屋上は、定期的なメンテナンスが必要です。屋上防水工事のメンテナンスのタイミングを解説します。
<h3>屋上防水の劣化症状</h3>
以下のような症状は、屋上の防水機能が劣化しているサインです。
| 劣化症状 | 詳細 |
| 色褪せ | 色褪せ自体に問題はないが、色褪せが起こると徐々に表面の剥がれやひび割れが始まる。色褪せの段階でメンテナンスをするのが望ましい。 |
| ひび割れ | トップコートや防水層にひびが入る症状。ひび割れが防水層まで広がっている場合早急な工事が必要。 |
| 剥がれ | 防水層が剥がれることで、雨水が内部に侵入してしまう。早急なメンテナンスが必要。 |
| 膨れ | 部分的なひび割れや剥がれから水が侵入し、防水層と下地の間に水蒸気が溜まる現象。早めの工事が必要。 |
| 水溜まり | 防水効果の低下や排水口(ドレン)の詰まりなどで発生する。排水口の掃除や防水層のリフォームで対応する。 |
| カビ・藻・植物の繁殖 | 防水効果の低下によって起こる。植物の根や茎が防水層や下地にまで侵食するおそれがあるので、早めのメンテナンスが必要。 |
上記のような劣化症状を放置すると、劣化箇所から水が建物内部に染みて雨漏りなどを引き起こす原因となります。屋上防水の劣化症状が見られたら、早急に工事を行いましょう。
耐用年数に達したとき
特に劣化症状が見られなくても、耐用年数に達したときには防水工事を行いましょう。先述したように、防水工事の耐用年数は工法や素材ごとに異なります。しかし、大体の目安として、施工後10年が経過したらメンテナンスを行うと良いといわれています。
防水調査を活用する方法も
ビルやマンションの場合、屋上や外壁の状態をこまめに確認するのは難しいのが現状です。また、一見劣化がないように見えても内部の防水層で不具合が進んでいるケースもあり、素人目では防水機能の劣化を判断しにくいでしょう。
そのようなときに活用したいのが、防水調査です。ビルやマンションの修繕工事を行う会社では、屋上防水の調査診断を行っているところがあります。屋上防水の耐用年数まで数年あるけれど劣化が気になるというときや、専門家の目線で防水機能の劣化状況を判断してほしい場合は、防水調査を依頼しましょう。
防水工事は修繕費用?資本的支出?
ビルやマンションの防水工事で節税する方法として、防水工事にかかった費用を「修繕費用」として計上するやり方があります。
ビルやマンションといった不動産に関わる工事費用は、「修繕費用」と「資本的支出」のいずれかに分類されます。修繕費用の場合、確定申告の際に経費として計上できるため、結果的に節税につながります。一方で資本的支出は、経費として計上することはできません。
防水工事の費用がどちらに分類されるかは、工事の内容によって決まります。
修繕費用とは必要最低限の工事にかかる費用
修繕費用とは、所有するビルやマンションなどの固定資産に不具合が起こった際に、原状回復のために行う修理やメンテナンスの費用を指します。
修繕費用に分類されるのは、劣化などによってマイナスになった機能や性能をゼロに戻すための工事費用で、あくまでも現状の資産価値を維持するためのものです。防水工事の内容がこれに該当する場合は、修繕費用に分類されます。
また例外として、資本的支出に該当する工事であっても、工事費用が20万円以下の場合は修繕費として計上できます。
修繕費用に該当する防水工事の例
以下のような防水工事は、修繕費用に該当します。
- 屋根の雨漏り止めるために行った防水工事
- 防水層のひび割れや剥がれの修繕工事
- 耐用年数に達したために行う定期メンテナンス
不具合が発生したり、耐用年数に達したりした際に行う工事は、資産価値の維持に分類されます。
資本的支出とは建物のアップグレードにかかる費用
資本的支出とは、所有するビルやマンションといった固定資産の原状回復や維持に加え、その価値を上げるために行う工事の費用を指します。ゼロをプラスにする工事、またはマイナスをプラスにするための工事です。
例えば、既存の防水性能をアップグレードするために行った工事は、資本的支出に該当します。
資本的支出に該当する防水工事の例
以下のような防水工事は、資本的支出に分類されます。
- 耐用年数が伸びるよう防水方法を変更する工事
- 修繕のついでに屋上に遮熱トップコートを塗装する工事
- 外壁塗装の際に、安くするためにまとめて行う屋上防水工事
不具合や劣化がない状態で、資産価値を上げるために行う工事が挙げられます。
屋上防水工事で業者に依頼する際の注意点
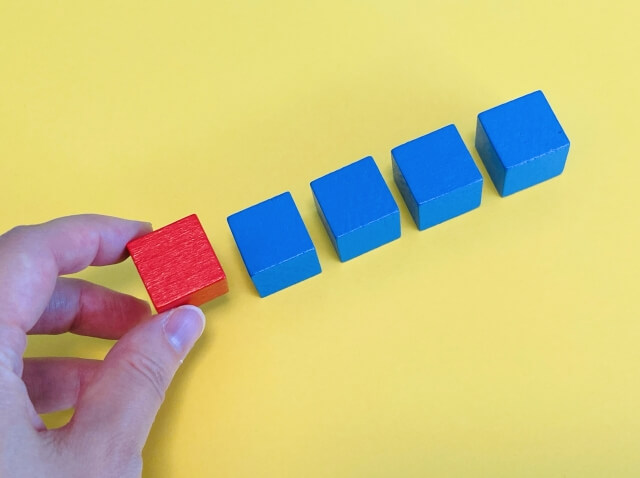
ビルやマンションの屋上防水工事を業者に依頼する際は、以下の点に注意しましょう。
- 業者に修繕の範囲内で防水工事したいと伝える
- 施工実績が豊富で技術力のある業者を選ぶ
- 節税対策の知識がある業者を選ぶ
- 相見積もりをする
1つずつ解説します。
業者に修繕の範囲内で防水工事したいと伝える
もし防水性能の維持やメンテナンスを希望しているのであれば、業者に依頼する際に「修繕の範囲内で防水工事をしたい」とはっきり伝えましょう。
特に要望を伝えず見積もりを依頼すると、防水工法や材質の変更など、業者側から建物のグレードアップに該当する工事を提案される可能性があります。最初から修繕費用の範囲内で防水工事をしたいと伝えておけば認識の齟齬を防げ、安心して工事を進められます。
施工実績が豊富で技術力のある業者を選ぶ
ビルやマンションなど大型の建物は、万が一施工不良があった際に負うダメージも大きくなります。特に防水工事に不具合があると、雨漏りなどで躯体全体が傷む可能性があります。業者を選ぶ際は、施工実績が豊富で技術力が十分にあるところを選びましょう。
施工実績は、それぞれの専門業者のホームページなどで確認できます。その際、自身が保有するマンション・ビルと似た形状の建物や、類似ケースの施工実績が多いかという点に注目しましょう。
また、資格保有者の人数は、技術力をはかる一つの指標となります。防水工事関連だと「一級防水施工技能士」や「一級樹脂接着剤注入施工技能士」「改質アスファルトトーチ工法施工技能士」などの資格があります。
節税対策の知識がある業者を選ぶ
防水工事を行ううえで節税対策を考えているなら、節税関連の知識や対応工事に理解のある専門業者を選びましょう。防水工事を行う業者には、一般住宅を得意とするところや大型の建築物を得意とするところなど、それぞれ強みがあります。
ビルやマンションといった大型建築の防水工事を専門に行っている業者であれば、費用の節税対策についてある程度知識があるかもしれません。施工業者でも判断が難しい場合は、税理士に相談しましょう。
相見積もりする
防水工事の専門業者を選ぶ際は、3社以上で相見積もりを行いましょう。
相見積もりを行うと防水工事の費用相場がわかるため、適正価格を提示する業者を見極めることができます。
また、見積もりの内訳を細かく記載しているかどうかも判断基準です。詳細をきちんと記載している見積もりであれば、工事内容に疑問がある際も質問しやすいでしょう。
屋上防水工事は耐用年数を念頭に入れて行おう
ビルやマンションの屋上は普段目にする機会が少ない分、防水性能の劣化状況がわかりづらいです。防水工事ごとの耐用年数はメンテナンス周期の目安となるため、なるべく把握しておきましょう。メンテナンス時期に迷っている場合は、専門業者による防水調査を活用するのもおすすめです。
防水の専門家に工事を依頼したい方は、ぜひ「屋上防水プロ」をご活用ください。