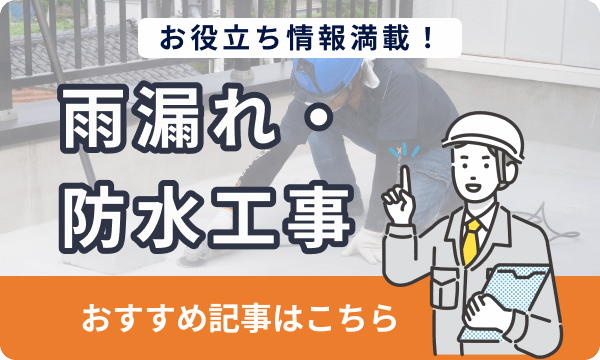<こんな疑問のある方におすすめ>
・防水工事を依頼したらウレタン防水を勧められたけど、実際どうなの?
・ウレタン防水が自分の家に合っているかどうか知りたい!
・ウレタン防水のデメリットってなに?
ウレタン防水はポピュラーな防水方法で、多くの住宅やビル・マンションに採用されています。今回はウレタン防水の特徴や工法の違い、メリットとデメリットを詳しく解説します。お手入れ方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ウレタン防水とは?
ウレタン防水とは、液体状のウレタン樹脂を複数回塗り防水層を形成する、ポピュラーな防水方法です。
ウレタン樹脂は液体状のため凹凸のある複雑な形状の建物にも対応でき、またウレタン樹脂を塗り広げて施工するのでつなぎ目がありません。別の防水材の上からでも重ね塗りできる使い勝手の良さも特徴です。
防水工事の中では比較的費用も安く、戸建てのベランダやバルコニー、マンションの屋上などさまざまな場所で採用されています。
ウレタン防水の3つの工法
ウレタン防水には、主に以下の3種類の工法があります。
- 密着工法
- 通気緩衝工法
- メッシュ工法
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
密着工法
密着工法とは、プライマーを塗布した下地の上に直接ウレタン樹脂を塗り広げていく工法です。塗膜は2層重ねられ、1層目を塗り終えた後に一度乾燥させる必要があります。
密着工法は3つの工法の中では比較的工期が短く済みますが、下地の影響を受けやすい点がデメリットです。下地の水分量が多い状態で施工すると、蒸発した水分が塗膜の膨れにつながり、防水層がひび割れを起こすおそれがあります。
マンションの屋上は、分厚いコンクリート内部までしっかり乾燥させるのが難しいため、密着工法には向いていません。戸建て住宅のベランダやバルコニーなど、面積が狭い箇所への施工が一般的です。
費用相場と耐用年数
| 費用相場 | 4,000~6,000円/1m2 |
| 耐用年数 | 7~10年 |
密着工法のウレタン防水は、費用相場が1m2あたり4,000~6,000円で、3つの工法の中でもっとも安価な傾向にあります。耐用年数は7~10年ほどですが、トップコートは5年ごとを目安に塗りなおしましょう。
密着工法の施工工程
密着工法は、以下のような工程で施工されます。
- 高圧洗浄や下地処理(目地やひび割れの補修など)
- プライマーの塗布
- ウレタン樹脂1層目の塗布
- ウレタン樹脂2層目の塗布
- トップコートの塗布
下地の状態が悪い場合は、プライマーを塗布する前に下地処理としてモルタルを塗布して補修することもあります。
密着工法の工期は、3~7日ほどです。
通気緩衝工法
通気緩衝工法は絶縁工法とも呼ばれ、大まかな工程は密着工法と似ています。異なるのは、プライマーを塗布した下地の上に通気緩衝シートを貼りつけ、その上からウレタン樹脂を2層重ね塗りする点です。
通気緩衝シートが下地に含まれる水分や湿気を吸収し、脱気盤という小さな煙突のような筒から放出されます。そのため水分の蒸発による塗膜の膨れが起こりにくく、雨漏りが発生した箇所や乾燥が難しいマンションの屋上など、水分を含む箇所にも施工できます。
通気緩衝工法はビルやマンションの屋上、アパートの屋根など、面積が広く平らな場所に施工されることが多いです。
費用相場と耐用年数
| 費用相場 | 5,000~7,000円/1m2 |
| 耐用年数 | 10~15年 |
通気緩衝工法は緩衝シートを挟む分、密着工法よりも費用が高くなりやすいです。しかし水分や湿気の影響を受けにくいため、耐用年数も長い傾向にあります。
通気緩衝工法も密着工法同様、トップコートの塗り替えは5年ごとに行うのが望ましいです。
通気緩衝工法の施工工程
通気緩衝工法は以下の工程で施工されます。
- 高圧洗浄や下地処理(目地やひび割れの補修など)
- プライマーの塗布
- 通気緩衝シートの貼りつけ
- 脱気盤の設置
- 改修用ドレンの設置
- ウレタン樹脂1層目の塗布
- ウレタン樹脂2層目の塗布
- トップコートの塗布
通気緩衝工法の工期は、7~12日ほどです。
メッシュ工法
メッシュ工法は、プライマーを塗布した下地の上にメッシュ状の繊維シートを貼りつけ、その上からウレタン樹脂を2層重ね塗りする工法です。シートを挟む点が通気緩衝工法と似ていますが、シートの持つ効果が異なります。
メッシュ工法はメッシュ状のシートが施工箇所全体を覆うため、防水層の強度が増す点が特徴です。また、耐震性も上がるといわれています。
しかし一方で、通気緩衝シートのように水分や湿気を吸収する効果はないので、下地が水分を含んでいる状態だと膨れが起こる恐れがあります。
メッシュ工法は、主に戸建て住宅のベランダやバルコニーに用いられます。
費用相場と耐用年数
| 費用相場 | 5,000~6,000円/1m2 |
| 耐用年数 | 10年前後 |
メッシュ工法は密着工法よりは費用が高いですが、通気緩衝工法に比べると安価です。耐用年数は10年ほどですが、耐震性は3つの工法の中ではもっとも高いといえるでしょう。
メッシュ工法も他の2つの工法と同じように、5年ごとを目安にトップコートの塗り直しが必要です。
メッシュ工法の施工工程
メッシュ工法は、以下の工程で施工します。
- 高圧洗浄や下地処理(目地やひび割れの補修など)
- プライマーの塗布
- メッシュシートの貼りつけ
- ウレタン樹脂1層目の塗布
- ウレタン樹脂2層目の塗布
- トップコートの塗布
メッシュ工法の工期は、6~11日ほどです。
ウレタン防水のメリット
ウレタン防水の主なメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 安価な費用で施工できる
- 複雑な形状にも対応できる
- 伸縮性が高い
一つずつ見ていきましょう。
安価な費用で施工できる
ウレタン防水の大きなメリットは、工事費用の安さです。
具体的に、他の防水工事と施工単価を比較してみましょう。
| 単価(m2) | 耐用年数 | 工期 | |
| ウレタン防水 | 4,000~7,000円 | 7~15年 | 3~7日 |
| FRP防水 | 6,000~9,000円 | 10~12年 | 1~2日 |
| シート防水 | 4,000~8,000円 | 10~20年 | 1~3日 |
| アスファルト防水 | 5,000~8,000円 | 15~25年 | 6~10日 |
工法によって多少上下はするものの、ウレタン防水は4つの防水方法の中ではもっとも安価です。
費用が安価な要因として、ウレタン樹脂材の材料費の安さや、職人の数の多さがあります。ウレタン防水はもっとも一般的な防水方法なため施工できる職人が多く、競争原理が働く分費用が安くなる傾向があるのです。
複雑な形状にも対応できる
ウレタン防水は液状のウレタン樹脂を塗布するため、凹凸のある複雑な形状にも継ぎ目なく施工できます。
例えばシート防水の場合、必ずシート同士の継ぎ目があり、施工箇所の形状が複雑になるほど継ぎ目が増えていきます。継ぎ目を合わせてうまく施工できないとそこから腐食が始まってしまうほか、経年劣化で継ぎ目からシートが捲れる可能性もあります。継ぎ目のないウレタン防水は、その分腐食や捲れのリスクが軽減されます。
また、ウレタン防水は既存防水層の上から重ね塗りできるため、防水層の撤去・処分費用がかかりません。どんな場所にも継ぎ目なく施工できる点は大きなメリットといえるでしょう。
伸縮性が高い
ウレタン樹脂は、ポリウレタンとも呼ばれるプラスチック素材でできています。ポリウレタンは柔軟性・弾力・防音性・耐衝撃性に優れており、防水以外にも洋服や接着剤など、さまざまなものに使われています。ウレタン防水は、こうしたポリウレタンの性能の高さを活かした防水方法といえるでしょう。
同じく塗膜防水のFRP防水は、膜が硬いため柔軟性に乏しい点がデメリットです。そのため、防水工事の際にFRP防水の上からウレタン防水を施すケースも少なくありません。
ウレタン防水のデメリット

メリットの多いウレタン防水ですが、デメリットも存在します。ウレタン防水の主なデメリットは以下の通りです。
- 塗膜の乾燥に時間がかかる
- 仕上がりが職人の技術に依存する
- 経年劣化で亀裂が入りやすい
それぞれ見ていきましょう。
塗膜の乾燥に時間がかかる
ウレタン防水は、塗膜が硬化するまでに時間がかかります。1層目、2層目の塗布の後にそれぞれ乾燥の時間を設ける必要があるため、硬化の早いFRP防水などに比べると工期が長くなってしまいます。また乾燥中は施工現場に立ち入ることができません。
施工面積が広くなるほど塗膜の乾燥に時間がかかるので、その分工期も長くなります。
仕上がりが職人の技術に依存する
ウレタン防水の防水層の厚さは、2~3mmが適正とされています。職人は施工箇所の防水層がすべて2~3mmの厚さになるよう、均一に塗り広げなければなりません。また、2~3mmの厚さを保ちながら、排水溝にスムーズに雨水が流れるよう注意して施工する必要があります。塗膜の厚みが均一でないと表面が凸凹になってしまい、うまく排水されません。
ミリ単位で厚みを統一し塗料を塗り広げていくには、高い技術力と経験が求められます。特に立ち上がりの部分は、技術の差が如実に現れます。仕上がりが職人の腕に左右されてしまう点は、ウレタン防水のデメリットといえるでしょう。
経年劣化で亀裂が入りやすい
ウレタン防水は塗膜防水のため、長期間紫外線や雨風にさらされると表面のひび割れや亀裂といった経年劣化が起こります。特に亀裂が防水層にまで至ると、雨漏りの原因になります。
こういった劣化症状はウレタン防水だからというよりも、塗膜防水のデメリットといえるでしょう。ひび割れや亀裂を起こさないためには、トップコートの塗り直しなどこまめなメンテナンスが必要です。
ウレタン防水の劣化のサイン
ウレタン防水は、雨や湿気、温度変化に加え、長期間の使用による摩耗や汚れの蓄積など、さまざまな要因で劣化していきます。
ウレタン防水の主な劣化のサインとして、以下が挙げられます。
- 表面のひび割れ・亀裂
- 防水層の浮き・膨れ
- 防水層の摩耗
- チョーキング
詳しく見ていきましょう。
表面のひび割れ・亀裂
ウレタン防水の表面のひび割れは、トップコートから始まります。トップコートのひび割れを放置していると、雨水が内部にまで侵入し、やがて防水層の亀裂や破断につながります。
ひび割れは、表面の凍結や融解によって加速する場合もあります。ひび割れを見つけたら、早めに修復しましょう。
防水層の浮き・膨れ
防水層の浮きや膨れは、防水層と下地の間に雨水が浸入することで起こります。防水層の内部に水が入り、その部分だけが膨れているため目視でも確認できます。
防水層の膨れは、密着工法で施工した場合に起こりやすい劣化症状です。表面に膨れている箇所や浮いている箇所があったら、早急に補修しましょう。
防水層の摩耗
防水層の摩耗は、雨風や紫外線によって防水材料が劣化し、それと共に防水層の厚みが減少していく症状です。経年劣化でトップコートが剥がれ、無くなってしまうことも原因の一つです。
防水層が摩耗し薄くなると、塗膜の破断や下地のひび割れ・剥がれなどが起こる可能性があります。防水層の摩耗は、防水性能を維持するためにも早急な修復が必要です。
チョーキング
チョーキングは、経年劣化により防水材料が粉状になってしまう現象を指します。チョーキングが進行すると塗膜の光沢がなくなり、表面のひび割れや防水層の剥がれへとつながります。
チョーキングを長期間放置すると防水層が激しく劣化し、ボロボロになる危険性があります。修繕の緊急度でいうと、ひび割れよりも高いため注意が必要です。
ウレタン防水を長持ちさせる方法
ウレタン防水を長持ちさせるためには、以下のようなメンテナンスが大切です。
- 表面の汚れを取り除く
- 排水溝(ドレン)に溜まったゴミを片付ける
- マットを剝がして換気・清掃する
- トップコートを塗り替える
ウレタン防水にとって汚れは大敵です。表面についた土埃や枯れ葉はこまめに取り除きましょう。ウレタン防水はデリケートなので、掃除の際は硬いブラシは使わず、ホウキや柔らかいモップを使用します。汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を水で薄め、布で優しく拭きましょう。
排水溝の詰まりは水たまりの原因となるため、枯れ葉などのゴミがある場合はこまめに取り除きます。また、湿気がこもらないよう、マットを敷いている場合は定期的に剥がして換気し清掃を行いましょう。
ウレタン防水はDIYでなく業者に依頼を
防水工事にはまとまった費用が必要になるため、DIYで済ませられないかと考える方もいるでしょう。しかし、防水工事をDIYするのはあまりおすすめできません。
防水層の形成には専門的な知識や技術が必要です。特にウレタン防水は、ウレタン樹脂を均一な厚さで塗り広げるのに経験やスキルが求められます。DIYで不完全な防水工事を行うと、後々不具合が生じ、かえって修繕費用がかかってしまう可能性があります。
防水工事は、専門業者に依頼しましょう。
ウレタン防水はメリットの多い防水工事!
さまざまな場所に施工でき費用も安価なウレタン防水は、メリットの多い防水方法です。とはいえ、仕上がりが職人の技術力に左右される、塗膜の乾燥に時間がかかるといったデメリットもあるため、業者に依頼する前にメリットとデメリットの両方をきちんと把握しておきましょう。
防水の専門家にウレタン防水工事を依頼したい方は、「屋上防水プロ」をぜひご活用ください。