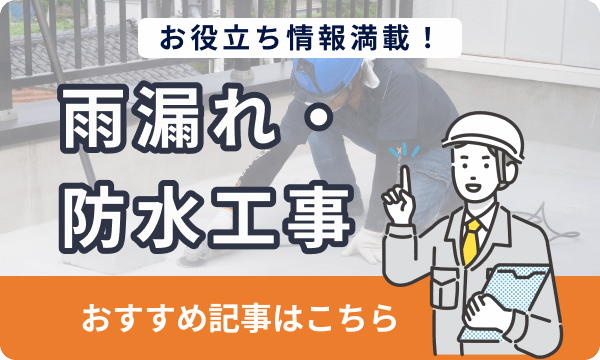<こんな疑問のある方におすすめ>
・ビル・マンションの屋上防水の耐用年数ってどれくらい?
・耐用年数には達していないけどメンテナンスした方がいい?
・屋上防水工事の費用相場を知りたい!
屋上は常に紫外線や雨風にさらされている場所であり、建物を守るためにも適切な防水工事が必要です。今回は、屋上防水工事の耐用年数やメンテナンス時期の目安、費用相場を解説します。ぜひ参考にしてください。
マンションの屋上防水は建物の保護に必要
屋上防水は、マンション全体の保護に欠かせません。屋上防水が不十分だと、劣化部分から雨水が入り込み、雨漏りの原因となります。建物の躯体部分にまで雨水が侵入すると、躯体の腐食や劣化、コンクリートの欠損などを引き起こし、寿命を大きく縮めてしまいます。
建物の防水性能をきちんと維持することが、マンションの劣化を遅らせ、建物全体の保護につながるのです。
マンションの屋上防水の耐用年数
マンションの屋上防水の耐用年数は、防水工事の方法によって異なります。
防水工事の種類別の耐用年数を以下にまとめました。
| 防水工事の種類 | 耐用年数 |
| ウレタン防水 | 密着工法:7~10年通気緩衝工法:10~15年 |
| FRP防水 | 10~12年 |
| シート防水(塩ビ・ゴム) | ゴムシート:10~15年塩ビシート:10~20年 |
| アスファルト防水 | 15~25年 |
マンションの屋上防水には、シート防水やアスファルト防水がよく採用されます。種類によりけりですが、大体10~20年を目安に考えると良いでしょう。
屋上防水のメンテナンス時期の目安
屋上防水のメンテナンス時期の目安として、主に以下の2つがあります。
- 耐用年数に達したとき
- 劣化が見られたとき
それぞれ見ていきましょう。
耐用年数に達したとき
特に劣化症状が見られなくても、耐用年数に達したら防水工事を行いましょう。
先ほど触れたように、屋上防水の耐用年数は工法ごとに微妙に異なります。しかし、一般的には10~20年が目安です。前回の防水工事から10年が経過したらメンテナンスを検討しましょう。
劣化が見られたとき
耐用年数に達していなくても、防水層に劣化が見つかった場合は適宜メンテナンスが必要です。紫外線や雨水、暴風や豪雪といった気候条件のほかに、屋上で長期間、人の行きかいがあったり、建築作業が行われたりしても劣化を早める原因となります。
劣化症状を見つけたら、なるべく早めにメンテナンスを行いましょう。
マンションの屋上防水の劣化症状
マンションの屋上防水のよくある劣化症状は以下の通りです。
- 表面の色あせ
- ひび割れ
- 継ぎ目の剥がれ
- 膨れ
- 笠木の劣化
- 水溜まり
- 破れ
- ドレンの目詰まり
- 雑草が生えている
どういったものか、具体的に見ていきましょう。
表面の色あせ
表面の色あせは、防水層の初期の劣化症状です。
色あせが発生してしばらくすると、ひび割れや剥がれといった本格的な防水層の劣化が起こります。表面の色あせの段階でメンテナンスをすれば、劣化の進行を止められる可能性が高まります。色あせに気付いたら、早めにメンテナンスを行いましょう。
ひび割れ
トップコートや防水層のひび割れは、乾燥による収縮や凍結・溶解などが原因となり発生します。
また、コンクリートには時間と共にコンクリート内部のアルカリ性が失われ、中性に近づいていく「中性化」という現象があります。このコンクリートの中性化も、ひび割れに影響するといわれています。
ひび割れは放置すると雨漏りの原因になるため、早急なメンテナンスが必要です。
継ぎ目の剥がれ
シート防水を施している場合、経年と共にシートの継ぎ目(ジョイント部分)が劣化し、口が開いて剥がれ出してしまいます。特に屋上の立ち上がり部分とシートを密着させているシーリングが劣化すると、剥がれが起きやすくなります。
剥がれた部分から雨水が浸入するのを防ぐため、メンテナンスが必要です。
膨れ
防水性能が低下すると、防水層の内側に結露が発生します。太陽光によって結露が温められ水蒸気になると、防水層に膨れが起こります。膨れはシート防水・アスファルト防水の継ぎ目やウレタン防水の塗膜でよく見られる劣化症状です。
膨れた部分は破れやすくなるため、さらに劣化を進める原因にもなります。放置せずなるべく早めにメンテナンスしましょう。
笠木の劣化
笠木部分が劣化し、ヒビやモルタルの欠損が起こると、立ち上がり部分の防水層に水が浸入し雨漏りにつながる場合があります。ヒビや欠損以外に、苔が生えている状態も防水性能の低下を示しています。笠木部分の状態もこまめに確認しておきましょう。
水溜まり
水溜まりは、地面の歪みや排水機能の低下などさまざまな要因で発生します。水溜まりを長時間放置すると、その部分の防水層が傷み、劣化のスピードを早めてしまいます。
排水溝の詰まりを掃除したり、シートなどで屋上に勾配をつけたりして、雨水が溜まらないよう注意しましょう。
破れ
破れた箇所から雨水が浸入し、雨漏りが起こってしまいます。
破れは、膨れが悪化して起こることもあれば、飛来物や鳥につつかれることが原因で発生するケースもあります。特にゴムシート防水は鳥害に弱いため、屋上にゴムシート防水を採用している場合は鳥よけなどの対策が必要です。
ドレンの目詰まり
雨水を排水するルーフドレンが詰まると、排水機能が落ちて水溜まりや雨漏りの原因となります。落ち葉やゴミなどでドレンが詰まらないよう、こまめに掃除しましょう。
雑草が生えている
屋上は風に乗って植物の種子が飛んでくることがあり、気付かないうちに雑草が生えてしまう場合があります。雑草の根の力はとても強く、表面を突き破って防水層まで伸びてしまうケースも少なくありません。
水が根を伝って躯体部分に侵入し、劣化を早める可能性があるため、雑草を見つけたら根が深く張る前に抜くようにしましょう。ただし、防水層まで根が張っていると、抜くことで防水層に穴を開けてしまうリスクもあります。根が深く防水層まで侵入している際は、専門業者にメンテナンスを依頼しましょう。
屋上防水工事の費用相場

屋上防水工事の費用は、施工費と諸費用の合計となります。
それぞれの費用相場を見ていきましょう。
屋上防水の種類別単価
防水工事の種類ごとの単価を以下にまとめました。
| 防水の種類 | 単価(1m2) |
| ウレタン防水 | 密着工法:4,000~6,000円通気緩衝工法:5,000~7,000円 |
| FRP防水 | 6,000~9,000円 |
| シート防水 | 4,000~8,000円 |
| アスファルト防水 | 5,000~8,000円 |
FRP防水がもっとも高いですが、伸縮性が乏しく広い場所の施工には不向きです。そのため、マンションの屋上にはほとんど採用されません。
防水工事以外の諸費用
施工費以外の諸費用は以下の通りです。
| 項目 | 費用相場 |
| 高圧洗浄費用 | 150~300円/1m2 |
| 下地処理・ケレン費用 | 200~500円/1m2 |
| 下地補修費用 | 1,000~1,500円/1m2 |
| 改修ドレン設置費用 | 20,000~25,000円/1箇所 |
| 脱気筒設置費用 | 約15,000円/個 |
| 発生材処分費用 | 10,000~25,000円/一式 |
| 諸経費(荷下ろし代など) | 10,000〜25,000円/一式式 |
| 足場設置費用 | 12万~15万円 |
上記にプラスして、工事費用の5~10%ほどの管理費用がかかります。
屋上防水工事は修繕費?資本的支出?
屋上防水工事は、建物の維持管理や防水層のメンテナンスを目的に行われることがほとんどです。
国税庁の基準では、修繕費とみなされるのは以下のようなケースのようです。
- 維持管理または原状回復を目的とした工事
- 工事費用が20万円未満または60万円未満
- 工事周期が3年未満
- 取得価額が前回の決算時の10%以下
一般的には、屋上防水工事は修繕費とみなされる場合が多いようです。
屋上防水工事の費用を抑えるポイント
屋上防水工事の費用を抑える主なポイントは以下の通りです。
- 相見積もりをする
- 閑散期に工事を依頼する
- 状態が悪化する前に工事を行う
防水層の劣化が進むほど工事の工程が増え、その分費用も高くなります。状態が悪化する前に工事を依頼すれば、必要以上の費用を払わず済むでしょう。
マンションの屋上防水の寿命を延ばすためには
マンションの屋上防水の寿命を延ばす方法として、以下が挙げられます。
- 劣化サインが出たらすぐ補修する
- ドレン周辺を掃除する
- トップコートを塗り直す
それぞれ見ていきましょう。
劣化サインが出たらすぐ補修する
軽い劣化症状であれば、範囲も小さく建物への影響もほとんどありません。しかし劣化サインを放置しておくと、ひび割れや剥がれなど症状が悪化し、雨漏りの原因になります。雨漏りは躯体へのダメージが大きい分、建物の寿命を縮めてしまいます。
劣化範囲が狭く、建物への影響が少ない段階で早めに補修すれば、防水性能自体も長持ちするでしょう。
注意したいのは、屋上防水工事を自分でやろうとしないことです。後述するトップコートの塗装程度なら大丈夫ですが、素人が不完全な屋上防水を実施すると、後々再工事が必要になる場合があります。必ず業者に依頼しましょう。
ドレン周辺を掃除する
目詰まりが起きないよう、ドレン周辺をこまめに掃除・点検しましょう。
ドレンが詰まると排水機能が落ち、水溜まりが発生します。先ほど触れたように、水溜まりは防水層の劣化スピードを早める原因となるため、水溜まりができない状態を維持することが大切です。
トップコートを塗り直す
マンションの屋上防水の寿命を伸ばすために、定期的にトップコートを塗りなおすことが必要です。
トップコートには防水層を保護する役割があります。トップコートが劣化すると、防水層が紫外線などの刺激に直にさらされてしまいます。なお、トップコートを塗りなおす際の適切な周期は5年に一度です。
屋上防水工事を行う際の注意点
屋上防水工事を行う際は、以下の点に注意が必要です。
- 工事期間中に発生する悪臭と騒音への対応
- 追加工事の発生
- 保証内容の認識違い・確認漏れ
- 工事の遅延の可能性
アスファルト防水を採用する場合、アスファルトを熱で溶かして施工するため独特の臭いが発生します。近隣住民やマンション住民から苦情が出ないよう、着工前にきちんと挨拶して、工事内容を説明しておきましょう。
また、現地調査が不十分だと着工後に追加工事を提案されることがあります。保証内容に関してもそうですが、着工前に業者ときちんと認識をすり合わせ、現状を把握しましょう。
また、屋上防水工事は天候に左右されます。特に雨天が続くと工事が遅延する可能性があります。天候次第で工事が遅れる可能性もあることを念頭に入れておきましょう。
定期的なメンテナンスで屋上防水の寿命を延ばそう
屋上防水は、建物を保護するためにも欠かせません。定期的にメンテナンスを行うことで、屋上防水の寿命を延ばすことができます。屋上防水の耐用年数は防水方法によって異なりますが、おおむね10~20年といわれています。前回の防水工事から10年が経過したら、メンテナンスを検討し始めましょう。
また、耐用年数に関わらず、劣化サインを見つけたら早めにメンテナンスを行うことが大切です。屋上防水の費用は、基本的には修繕費で計上できるケースが多いです。しかし、工事内容によっては資本的支出に分類される場合もあるので、適用条件をよく確認しておきましょう。
防水の専門家に工事を依頼したい方は、ぜひ「屋上防水プロ」をご活用ください。